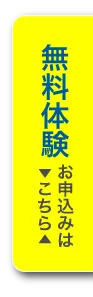夏休みも終わり、普段の生活に戻りつつある今日この頃、皆さんは夏休みの宿題にどんな思い出がありますか?親御さん世代にとっては、「長かった夏休みが終わってくれた!」とホッとしている方も多いのではないでしょうか。
そんな夏休みにつきものなのが「宿題」ですが、最近では「宿題代行サービス」なるものが登場しているのをご存知でしょうか?特に読書感想文は1枚3,000円という価格で、依頼者の趣味やスポーツ、心情に合わせて作成してくれるというから驚きです。
今回は、この宿題代行サービスと、そもそも学校教育における宿題のあり方について、私なりの考えをお話ししたいと思います。
学校教育の根深い問題点
宿題代行サービスが生まれる背景には、学校教育の抱える根深い問題が隠されていると私は考えています。親御さんからすれば、「こんな宿題をやる時間があるなら、塾で勉強させたい」「お金を払ってでも他の人にやってもらいたい」という思いがあるのではないでしょうか。
しかし、なぜ子どもたちは宿題の意味を理解できないのか?なぜ「やらされ感」が蔓延してしまうのか?私は、その原因の一つに、学校側が宿題の目的や意義を子どもたちに十分に伝えていないことがあると考えています。
子どもたちが「なぜこの宿題をやるのか」を理解していれば、たとえ親に「塾の勉強があるから」と言われても、「いや、僕はこれを学ぶべきだと思うから自分でやるんだ」と主体的に取り組むはずです。しかし、現状はそうではないからこそ、親の言いなりになったり、代行サービスに頼ったりする状況が生まれてしまうのです。
私の学習塾Nozomiでは、基本的に宿題を出しません。出すのは、次の授業で困るだろうという最小限の宿題のみ。それも「なぜこの宿題が必要なのか」を明確に伝えます。なぜなら、強制的にやらされるものは意味がないと私は考えているからです。
「読書感想文」を自力で書くべき理由
夏休みの宿題には様々なものがありますが、私が唯一「これだけは自力で絶対にやるべきだ」と考えているものがあります。それは、読書感想文です。
なぜ読書感想文なのか?それは、読書が「インプット」、感想文が「アウトプット」という、学びのサイクルを形成するからです。感想文を書くというアウトプットがあるからこそ、子どもは本を真剣に読み込み、内容を深く理解しようとします。
現代の子どもたちは読解力が低下していると言われています。活字を読む習慣が少なくなり、自分の言葉で表現することが苦手な子どもが増えていると感じます。読書感想文は、本を読む習慣をつけ、読解力と表現力を養うための非常に効果的なツールなのです。
それは、単なる宿題ではなく、知的好奇心を満たす貴重な時間となるでしょう。
AIに感想文を丸投げするのではなく、自分の言葉で表現することで、思考力や感情を整理する力も育まれます。AIは添削には活用できますが、読書体験そのものや、そこから生まれる思考のプロセスを代替することはできません。
「やらされ宿題」から「主体的な学び」へ
読書感想文以外の宿題、例えば「三桁×二桁の計算を何十問も解く」といった類のものには、正直なところ疑問を感じます。大人になって筆算を使う機会はほとんどありませんし、電卓やエクセルを使えばすぐに解決できるからです。仕組みを理解することは重要ですが、過度な反復練習は「やらされ感」を生み、子どもの学習意欲を低下させるだけだと私は思います。
宿題に追われる子どもたちの様子を想像してみましょう。
これは、本来の学びの姿とはかけ離れているのではないでしょうか。
今後、AIやテクノロジーがさらに進化する社会においては、自分で学び続ける力、知識をアウトプットする力がますます重要になります。そのためには、子どものうちから「やらされ宿題」ではなく、自ら課題を見つけ、解決しようとする「主体的な学び」の習慣を身につけることが不可欠です。
学校側も、宿題の本来の意味を子どもたちに伝え、彼らが主体的に取り組めるような工夫をしていくべきだと強く感じています。夏休みという貴重な時間を、子どもたちが本当に成長できる「学びの場」に変えていくために、大人たちがもっと真剣に考える必要があるのではないでしょうか。