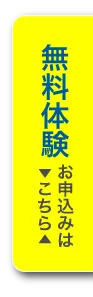親が奪う「考える力」
子どもが自分で考えられない——これは授業をしていてよく感じる現象です。もちろん全員ではありませんが、特に優しい親御さんや、面倒見の良い兄姉がいる弟などは、その傾向が強いように思います。
たとえば割合を求めるプログラムを作るとき、割合の計算式を忘れている中学生がいました。「今、消費税は何%?」と聞くと、「1%ですか?」と返ってくる。
この事実が示すのは、知識の欠如よりも「日常で考える習慣がない」ということ。買い物をしても、消費税が加算される理由や、そのお金の使われ方に興味を持たない——その結果、政治や選挙にも無関心になっていくのです。これは偶然ではなく、多くの場合、親の関わり方が原因です。
やらせるか、やってしまうか
電車に乗る場面を想像してください。親が切符を買い、改札に入れ、降りる駅で子どもを手を引いて出る——これでは子どもは何も考えずに目的地へ着けてしまいます。
一方、考える力を育てる親は違います。「行き先までの運賃を見てごらん」「子ども料金はいくら?」と問い、財布からお金を出させ、切符を買わせる。改札も路線図も自分で確認させる。
途中で乗り間違えてもいいのです。「じゃあどうすればいい?」と考えさせることで、失敗が学びに変わります。確かに親がやった方が早くて楽。しかし、それでは子どもはいつまで経っても自立できません。
送り迎えが大変だからと通学を諦める前に、子ども自身に交通手段や時間を調べさせる方が、将来の力になります。
小さな失敗が大きな成長に
醤油をこぼした、テーブルを汚した——そんな小さな失敗も、成長のチャンスです。「危険を伴わない失敗」は、どんどん経験させればいい。自転車の乗り方を兄姉や友達から学ぶのも同じで、教える側も「どう伝えればいいか」を考える貴重な機会になります。
便利さや安全を優先しすぎて、親がすべて先回りしてしまうと、子どもは「自分で考える必要のない人間」になってしまう。中高生になったら、自分で予約し、時間管理をさせる——こうした積み重ねが、答えのない時代を生き抜く力になります。
親がすべてを管理し続けるのではなく、あえて任せ、失敗させ、考える機会を与えること。それこそが、子どもの未来を守る一番の方法なのです。