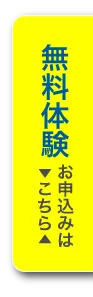子どもが育つ社会の“土台”が崩れ始めている
2024年、日本の年間出生数がついに70万人を下回りました。この数字、どれほどの重みがあるか想像できますか?
2015年には約100万人の子どもが生まれていたのに、わずか10年で3割減。これは単なる少子化ではなく、社会の基盤が音を立てて崩れている兆しです。
子どもが減るということは、教育環境、社会保障、地域コミュニティ、そして経済そのものにも大きな影響を与えます。私たちの子どもが成長する未来は、今とはまったく違う景色になっている可能性があります。
生きる力を育てる教育がますます重要に
子どもが減れば、当然ながら将来の働き手も減っていきます。その影響は、年金制度の破綻や税収の減少、インフラ整備や治安維持の難しさといった形で社会に表れてくるでしょう。
これは、単に「国の問題」ではありません。私たちの子どもが生きていく環境そのものが、確実に厳しくなっていくということなのです。
こうした時代に求められるのは、「いい学校に入る」だけではない力です。社会の変化を正しく理解し、自分で考え、柔軟に対応できる力――いわば“生きる力”を育てる教育こそが、これからの時代に必要とされていくでしょう。
親が残すべきは「学歴」ではなく「生き抜く知恵」
私たち親は、当然ながら子どもよりも先に人生を終えます。仮に親が80歳まで生きるとしても、30歳差の子どもはその後50年近くを「親なし」で生き抜いていかなくてはなりません。
つまり、子どもに残すべきものは、一時的なサポートではなく、長い人生を自力で歩むための「考える力」や「働く力」なのです。
そのためには、今から家庭の中で、学校では得られない学びを育んでいくことが大切です。プログラミングやITリテラシー、読解力、国際的な視点。そうした“世界でも通用する力”を、私たちがどう伝え、育てていくか。教育の本質が、今まさに問われています。